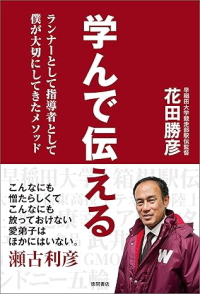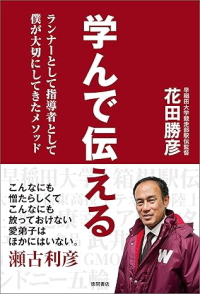|
ダイナミックで伸び伸びとトラックを疾走するその姿は、今でも私の脳裏に焼き付いている。
忘れもしない1996年の日本選手権10,000mは、アトランタオリンピック代表選考を兼ね、男女とも歴史に残る名勝負が繰り広げられた。
とりわけ男子10,000mのラスト2周から、著者を先頭に、渡辺康幸、平塚潤のエスビー食品勢と、虎視眈々とチャンスを伺う高岡寿成の4名によるデッドヒートは、陸上競技を始めたばかりの高校生(私)に、トラック競技とはこれほどまで激しく、魅力的なスポーツであることを教えてくれたレースでもあった。
しかし肝心のオリンピック本番では、実力を出し切れず予選敗退に終わった。
4年後のシドニーオリンピックはマラソンでの出場を目指したが叶わず、再び10,000mで代表を勝ち取り、見事に予選突破するが、決勝では不完全燃焼の15位でゴールした。
同レースで7位入賞した高岡に対し、予選の調子からいえば、私にも出せないタイムではなかった。ただ、私自身は、ケガもあって、目標を予選突破に置いていた。一方、高岡さんはアトランタオリンピックで予選敗退したあと、このシドニーオリンピックでは決勝進出はもちろん、入賞という一段上の目標をもって取り組んでいた (P180)と、高い目標に向けて準備することの大切さを痛感した。
それらの貴重な経験が、著者の指導哲学に表れている。
選手引退後は新興の上武大学の指導者となり、箱根駅伝初出場を決めた予選会では、選手たちに「君たちはこのレースに向けて120パーセントの努力をしてきたから、今日は8割5分の力を出せれば絶対に予選会は突破できる。もし、ダメだった場合は練習メニューを組んだ私が悪いので、すべての責任を取る」 (P174)と送り出した。彼らはレース後半でも笑顔で伸び伸びと走り、予選会3位の好成績で同校を箱根駅伝初出場に導いたことは、当時驚きをもって報道されていた。
新興校ゆえに選手勧誘に関する苦労も綴られているが、初出場から著者が同校を去るまでの8年連続で箱根本戦へ出場し、その後も3年続けて予選突破する礎も築いた。
一方で、集団走中心の予選では安定感あるものの、本戦では苦戦が続いた。
いずれはオリンピックに挑む選手を育てたいという強い思いもあり、実業団チームを創設したばかりのGMOインターネットグループに転じ、優秀な選手を育成してきたが、在籍した6年間でニューイヤー駅伝の最高順位は5位と、十分な結果を残すことができなかった。
私自身の理想と、思うようにいかない現実とのジレンマを抱えて、いつしか心身ともに疲れてしまい、ついには現場を離れることを決めた。半年から1年くらいは穏やかに暮らそうと考えていた (P7)が、恩師・瀬古利彦の仲介で母校・早稲田大の指導者に就任した。
期待されるのは大学駅伝での復活はもちろんだが、「早稲田から世界へ」という高い視座は決しておろそかにしてはいけない (P225)こともまた、伝統校ゆえの重圧だろう。
自身が学生時代に経験した海外遠征が、その後の成長につながるターニングポイントでもあったことから、現役学生にもその後押しをし、飛躍につなげる選手も出てきたそうだ。
これから著者のもとからどんなスター選手が誕生するのか、楽しみに見守りたい。 |